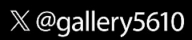Past Exhibition

Hiro TOBE 写真展「Rue Verneuil, Paris」
2020年4月6日(月)〜4月11日(土) 政府による緊急事態宣言が発令されたことにより終了となりました。
Si le printemps ne revenait plus
La rue était calme et ensoleillée comme avant. Je marchais sur le trottoir serré. C’était comme la veille que j’y étais venu la dernière fois. Midi passé, j’allais à un restaurant du quartier. Il faisait plutôt doux malgré la saison. On était en fin de février. On sortait sans manteau dans la journée.
Aurait-on dit l’été indien. C’était une image fréquente chez Modiano, me disais-je. Elle était étroitement liée à son idée de la saison éternelle où tout se répétait et se mélangeait. Un autre auteur que j’aimais, Simenon, aurait préféré « la Saint Martin » pour insinuer l’automne de la vie. Dans un de ses romains, un homme entre deux âges en avait été hanté. Ces deux expressions désignaient un moment avant l’hiver, n’auraient pas été correctes pour cette journée en fin d’hiver. Je voulais prendre part du « printemps précoce » pour la douceur de l’air.
Je revenais à Paris depuis quelques jours, sillonnais les quartiers après une longue absence. Je n’avais qu’une semaine pour combler le vide, avais hâte de reprendre la sensation d’avant le départ. Des fois je n’y arrivais pas. Certaines pièces étaient perdues comme d’autres restaurants ou des boutiques où j’étais allé si souvent. Modiano avait dit que les gens et les choses vous quittaient un jour. Du moins, les gens avaient vieilli, les lieux familiers avaient disparu sans vous le dire. Mais c’était moi qui avais quitté Paris, … pour quelques temps.
Je tournais à la rue Verneuil, poussais la porte du restaurant. Il était un des derniers d’avant qui me restaient encore. Je prenais le déjeuner dans la salle déserte. Les mêmes plats, les mêmes vins. Le même serveur discret qui me reconnaissait sans me le dire. Le décor n’avait pas changé. La lumière tamisée, les miroirs mouchetés, le clair-obscur réservé. La quiétude du midi était soulignée par les moindres bruits. Je pensais « comme c’était hier ».
Tout était comme la première fois que j’y étais venu. Plus de trente ans avaient passé, c’était l’été de mes vingt ans, mon premier séjour en France sans mes parents. Il avait fait beau comme ce jour-là, mais avec beaucoup plus de lumière et de chaleur. Il avait fait frais dedans.
Depuis, j’avais pris l’habitude d’y revenir à mes séjours parisiens. Je revoyais encore certains moments dans ce lieu tant apprécié. Mais leurs images n’étaient jamais précises. Un peu plus nettes dans le centre, elles devenaient troubles vers les bords avant de s’estomper. Les dates aussi se confondaient, je ne pouvais plus déterminer l’époque pour la plupart d’elles.
Je sortais dans la rue. Le digestif offert faisait son effet, brouillait les pistes, mais lesquelles ?
Je me dirigeais vers la lumière. La rue de Poithier était déserte, presque blanchie sous le soleil. Les immeubles et les anciens hôtels particuliers offraient les pierres calcaires. Elles étaient douces, crémeux et rayonnantes. Soyeuses comme le vin de tout à l’heure. Je les caressais et goûtais, comme j’avais fait avant, depuis mon enfance. J’avais l’impression d’avoir flairé l’éternité. Peu importaient les graffiti des murs et les peintures écaillées des volets, les murs étaient là, depuis toujours.
La lumière était devenue plus forte qu’avant le repas, me renvoyait à cet été-là, et à ces beaux jours du mai de mes trente ans et quarante ans. Elle éclairait beau mes pistes d’antan, m’aveuglait au contraire. Elle mélangeait les saisons et les temps déjà révolus, en faisait un moment unique et éphémère. Je le grignotais en peu de jours qui me restaient. C’était mon printemps précoce.
Je cheminer vers l’hôtel. La musique s’échappait en sourdine par une porte
de service entrebâillée.
« … à quoi bon nier, ce qui m’ensorcèle c’est… »
J’allais me déboucher sur le boulevard. Je voyais les passants en tenu léger. A ce moment-là, je me suis enfin avisé qu’il n’y aurait plus de « printemps précoce » , si le printemps ne revenait plus.
Hiro TOBE
もしも春が来なくなったら
通りは以前と同様、静かで日当たりが良かった。狭い歩道を歩いていた。最後にここを通ったのがつい昨日のように思えた。午過ぎだったので、近くのレストランへ行こうとしていた。本来は寒い季節にもかかわらずどちらかと言えば暖かかった。2月の終わりだった。日中はコート無しで出かけていた。
こういうのはインディアンサマー(小春日和)と言うのだろう。モディアノの小説に良く出てくるイメージだと思った。全てが繰り返され混じり合う永遠の季節、という彼の考えと密接な関係のイメージである。私のもう一人のお気に入りの作家であるシムノンならば、(小春日和の頃にある)サンマルタンのお祭りという書き方を選んで、人生の秋を匂わせるだろう。ある小説に出てくる中年男は、頭の中でこの言葉につきまとわれていた。いずれにせよ冬の前の一時期を指しているので、どちらの言い方も正しいとは言えないだろう。むしろ、この陽気を考えれば早すぎた春、という表現の方が良いと思った。
私は数日前からパリに戻って来ていた。長らく不在にしてしまった街をあちこち歩き回っていた。空白を埋めようにも時間は一週間しかなかった。前の感覚を取り戻すのに焦っていた。特定のピースが無くて上手く行かないことも時にはあった。別のレストランやお店など、ずいぶん良く行っていたのに無くなってしまった所のことだ。モディアノが書いたように、人も物もある日あなたの許から去っていくのだ。少なくとも、人は歳を取っていたし、馴染みの場所も黙っていつの間にか無くなってしまっていた。とは言え、パリを離れたのは私の方だった、ほんのしばらくのつもりだったのだが。
ヴェルヌイユ通りに曲がると、レストランの扉を押して中に入った。そこは前から知っていた店の中で、まだ私に残されていた所の一つだった。他に客のいない店内でお昼を食べた。同じ料理に同じワイン。控え目なボーイも昔と同じで、私のことに気付いてはいたが、口には出さなかった。中の造りも何一つ変わっていなかった。レース濾しの光、わざと腐食させてまだらになった鏡のパネル。抑え気味の明暗。ちょっとした物音が却って昼日中の静けさを際立たせていた。「まるで昨日のことのようだ。」と、思った。
全てが初めてここに来た時と同じだった。あれからもう三十年以上が過ぎていたのだった。それは二十歳の夏、両親から離れて初めて一人でフランスを訪れた時のことだった。その日も良い天気だったが、もっと明るくずっと暑かった。店の中は涼しかった。それ以来、パリにいる時はそこを訪れるのが習慣になった。自分が好きなこの店で過ごした時のことは、今でも目に浮かぶ。でもその映像ははっきりすることはない。真ん中は多少くっきりしてはいるが、周辺に行くとぼんやりしてきて、かき消されてしまう。日にちもあいまいになり、殆どの場合はいつの時代かも分からなくなってしまった。
私は通りに出た。ご馳走になった食後酒が効いて来たようだった。もはや、足跡は見分けがつかなくなってしまっていた。とはいえ、何の足跡だったのだろうか。
私は明るい方に向かって行った。ポワトゥー通りは無人で、光で漂白されたようだった。マンションや昔の屋敷は石灰岩で建てられていた。石は優しく滑らかで輝いていた。先程のワインと同じく絹の喉越しだった。私は石を撫で、感触を味わっていた。以前と同じように、子供の頃からしていたように。永遠な何かに触れたような気がした。落書きや鎧戸の塗料の剥がれなど何でもなかった、壁はずっと昔からそこにあるのだった。
光は食事の前よりもよりも強くなっていた。あの夏や、三十代や四十代にパリで過ごした五月の美しい日々が帰って来たような気にさせられた。その光はかつて私の歩いて来た足跡を照らしてはいたものの、目が眩んで却って良く見えなくなっていた。季節の違いも、とっくに終わってしまった時代も、全部がないまぜになり、唯一の、しかもすぐに消えてしまいそうな瞬間になっていた。自分に残されたわずかな日にちでそういう瞬間を未練がましく少しずつ味わっていた。それが私の「早すぎた春」だった。
ホテルに帰ろうと歩いていたら、半開きの勝手口から、音楽がかすかに漏れているのが聞こえて来た。
「… 誤魔化してもしょうがないわ、あたしを虜にしているのは… 」
私は大通りに出ようとしていた。軽装の通行人が見えて来た。その時ようやく私は気がついた。もし春が来なくなったら、早すぎた春などもはや存在しないのだ。
Hiro TOBE
<新型コロナウィルス感染症に対する感染予防対策について>
オープニングレセプションやトークショーなどのイベントはございません。
また、会場内の入場者数が一度に多くなる場合には、順次ご入場いただくようにさせていただきます。